もくじ
なぜこの記事を書くのか
「医師の働き方改革のために診療看護師(NP)を活用」
「NPが医師不足を補う」
「NPは医師のタスクシフトを推進する」
医療現場で、あるいはメディアで、こうした説明を目にすることがあります。
そして、時にはNPが自らそのようなことを語ることさえあります。
このような言葉に、私は強い違和感を覚えます
突然ですが、少し奇妙な問いかけをさせてください。
「看護師は患者さんのために働く」 と言った場合、当たり前すぎる話かと思います。
「看護師は医師のために働く」 と言ったら、誰もがおかしいと思うはずです。
では、これはどうでしょう。
「診療看護師(NP)は医師のために働く」
なぜか、この言説は「医師の働き方改革」の文脈で、受け入れられてしまっていないでしょうか。
これは、ちゃんちゃらおかしい話です。
NPも看護師です。なぜNPになった途端、働く目的が「医師のため」にすり替わるのでしょうか。
この記事では、NPの役割を「タスクシフト」という言葉で説明することの問題点と、私たちが本当に守るべき価値について考えていきます。
タスクシフトとは何か(そして、何でないか)
まず、用語を整理しておきましょう。
本来の意味での「タスクシフト」とは、責任と権限を移管し、移管された側の独立した判断で業務を遂行することを指します。
医療現場で「タスクシフト」や「タスクシェア」という言葉をよく耳にしますが、実は日本の多くの現場で起きているのは正確には「タスクデリゲーション(業務委任)」です。
多くの場合、最終的な責任は委任元の医師に残り、看護師は医師の指示のもとで業務を行います。
しかしこの記事では、正確ではないと認識したうえで、わかりやすさを重視して、一般的に使われている「タスクシフト」という言葉を使用することとします。
タスクシフト:責任と権限を移管
タスクシェア:責任と権限は共有
タスクデリゲーション:業務を一時的に委任(最終責任は委任元に残る)
「タスクシフト」という言葉が生む3つの誤解
NPの役割を「医師のタスクシフト」と説明すると、意図せず次のような誤解を招きます。
誤解1:NPは医師の代替品である
「タスクシフト」という言葉は、「医師の仕事を他の職種に移す」というイメージを強く持ちます。この視点では、NPは「医師ができない仕事を代わりにやる存在」として位置づけられてしまいます。
しかし、これは根本的に間違っています。
NPは医師の縮小版でも、代替品でもありません。
看護の専門性を基盤としながら、医学的知識を統合して患者ケアを行う、独自の役割を目指すべきなのです。
ここで、「専門性」について少し考えてみましょう。
専門職の本質は、体系化された知識とそれに基づく実践にあります。
医師は医学という知識体系を、看護師は看護学という知識体系を基盤としています。
欧米のNurse Practitionerは、看護学を基盤としながら、医学的知識を統合した独自の知識体系を持つ専門職です。
だからこそ、「NPが医師の仕事を代替できる」という発想は、根本的に間違っています。
これは両方の専門職に対して失礼な考え方です。
医師が長年学んできた医学という知識体系を、NPが完全に代替できるはずがありません。
同様に、看護師が培ってきた看護学の知識体系も、医師が代替できるものではありません。
誤解2:NPの価値は「医師の負担軽減」で測られる
「タスクシフト」を強調すると、NPの評価基準が「どれだけ医師の時間外労働を減らしたか」という指標に偏りがちです。
実際、日本でのNPの文献を見ると、それをアウトカムにしているものも散見されます。
しかし、これではNPが行うアセスメントやケアの本質的な価値が見えなくなってしまいます。 本来のNPの価値は、患者さんに対するアウトカムで評価すべきです。
誤解3:NPの存在意義は医師次第である
「医師の働き方改革のため」という文脈でNPを語ると、あたかもNPの存在意義が医師の都合に依存しているかのような印象を与えます。
これは専門職としての自律性を否定するメッセージです。
NPに限らずすべての医療職は「患者のため」に存在しているのです。
目的と結果を取り違えてはいけない
ここで、論理を整理しましょう。
- 目的:タスクシフト、医師の負担軽減
- 手段:NPの活用
- 結果:(期待として)患者利益
- 目的:患者への最適なケア
- 手段:NPの専門性発揮、多職種協働
- 結果:(副産物として)タスクシフト、医師の負担軽減
構造の違いがわかるでしょうか。
タスクシフトは、NPを含む各専門職が患者さんのために最善を尽くした「結果」であるべきで、決して「目的」ではないのです。
この論理に対し、「NPによるタスクシフトに異論を唱えるなら、タスクシフトでないNPの働き方を示すべきでは?」という反論が出ることがあります。
しかし、これは論点のすり替えです。
私はタスクシフトという現象を否定しているのではありません。 それを目的として語るべきではない、と主張しているのです。
医師の負担を軽減することは確かに大事です。
しかし、それは今まで医師に多大な仕事を押し付けてきた医療システムの問題を是正することです。
システムの問題を是正した結果、利益を得るのは誰でしょうか。医師でしょうか。
患者さんです。
適切な役割分担がなされることで、医師はより専門性の高い医療に専念でき、NPは看護の視点を活かした包括的ケアを提供できます。その結果、患者さんはより質の高い医療を受けられるようになります。
患者さん中心に考え、最善を尽くした結果、タスクシフトが起きます。
しかし、NPの目的はあくまで患者さんです。
なぜ「患者のため」と声に出して言う必要があるのか
「患者さんのためだなんて、当たり前すぎて言う必要ない」と思うかもしれません。
しかし、2025年現在の日本のNPは民間機関の認定資格にすぎず、新しくまだまだ発展途上で、社会に十分に認知されているとも言えません。
その状況で、NPが自らをどう語るかによって、NPの未来が決まります。
「何を大袈裟な…」と思われるかもしれませんが、人間には「同じ情報でも、伝え方によって受け取る印象が異なる」という認知バイアスがあります。
これをフレーミング効果といいます。
どのようなフレームでNPを語るかが重要なのです。
もしNP自身がタスクシフトの文脈で語れば、社会もそのように認識します。
「医師の代替」と誤解されれば、患者さんの信頼を損ない、結果的に誰の利益にもなりません。
NPの社会的認知が低いからこそ、NPが何のために存在するのか、社会に対して明確なメッセージで説明する責任があるのです。
「当たり前」のことだったとしても、繰り返し、広く発信する必要があります。
国家資格化という視点から考える
「NPをタスクシフトの文脈で語るべきでない」と考えるもう一つの理由があります。それはNPの国家資格化です。
2025年現在、国家資格としてのナース・プラクティショナー(仮称)の制度創設に向けて、日本看護協会、日本看護系大学協議会、日本NP教育大学院協議会の三団体で協議と調整が進められています。
NPが国家資格として認められることを目指すなら、「医師の働き方改革に貢献するから」という理由では、社会的な支持は得られにくいでしょう。
「それなら医師を増やせばいいのでは?」という当然の疑問に答えられないからです。
NPが専門職として認められるためには、もっと本質的な理由を提示する必要があります。
例えば:
- 国民への医療アクセス改善
- 医療の質向上
- 看護と医学を統合した新しい専門的価値の提供
などです。
病院の経営改善、医師の負担軽減、人件費削減などは、国家資格化の根拠としては不十分です。
それらの話は、組織内での活動としては重要ですが、新しい国家資格を創設する社会的正当性とは別の問題なのです。
「組織がNPにタスクシフトを求めている」について
「経営陣がNPに『医師のタスクシフト』を期待している」という声もあるでしょう。
実際のところ、組織の経営陣がNPに「医師のタスクシフト」を期待するのは無理のないことだと思います。
医師の時間外労働の上限規制、人件費の高騰、採用難。
一方、NPは医師より人件費が安く、特定行為などをある程度の指示の範疇で実施でき、柔軟に配置できる。
経営的には魅力的に映ります。
組織の中で働く以上、こうした経営方針を理解し、ある程度配慮する必要があることも事実です。経営陣の要求を完全に無視して働くことはできません。
しかし、それは経営陣の「組織の論理」であって、NPの「専門職の論理」とは異なります。
また、「経営陣の要求に応えること」が、私たちの存在意義の全てではありません。
組織の論理と専門職の論理
病院・組織が求めることと、専門職が自己を規定すべきことは、必ずしも一致しません。
組織の論理: 経営効率、コスト削減、組織の利益 など
専門職の論理: 患者への貢献、専門性の発揮、社会的使命、公共の利益 など
両者は時に矛盾することもあります。
NPが専門職であることを目指すならば組織の要求を理解しつつも、自律的に自己を規定すべきです。
経営陣への説明は戦略的に
経営陣に対しては、経営的メリットも含めて説明することは重要です。
しかし、それは説明の仕方の問題であって、NPの存在意義そのものではありません。
組織に求められるから「タスクシフトします」ではなく、患者のために最善を尽くした結果「タスクシフトが起きます」という、ちょっとした言葉の違いですが、この違いを意識することで、経営方針に逆らうことなく、専門職としての自律性を保つことができます。
また、医師の労働時間の短縮以外にも、医療の質向上、患者満足度、多職種協働、そして長期的な組織のブランドの成長など、これらもまた、経営陣の重要な要求のはずです。
NPの価値を「タスクシフト」という短期的な視点だけで捉えるのは、経営的にも視野が狭いと言わざるを得ません。
あなたの「やりがい」はどこから来るか
ここで、もう少し個人的な視点から考えてみましょう。
仕事の目的が違えば、日々のやりがい(内発的動機づけ)も変わってきます。
実際にやっていることは変わらなくても、自分の仕事の目的をどう捉えてフレーミングするかが大事です。
少し想像してみてください。
- 誇り:医師の仕事を手伝えたこと
- やりがい:医師に感謝されること
- 社会的評価:便利な代替要員
- 誇り:患者さんの健康に貢献できたこと
- やりがい:自らの専門性を発揮できたこと
- 社会的評価:自律した専門職
どちらが、専門職としてより魅力的でしょう。
未来の優秀な人材がどちらの姿に憧れるか、明らかではないでしょうか。
「タスクシフト」をどう語るか
日々の実践を報告する場で、タスクシフトをどのように語れば良いでしょうか?
医師の労働時間の短縮はひとつのアウトカムなので提示するのは悪くはないですが、フレーミングの仕方ひとつで受ける印象はだいぶ異なります。
「NPによる医師のタスクシフトで、医師の時間外労働がXX時間削減されました」 ではなく、
例えば、
「NPが患者さんへ包括的なケアを提供したことで、医師はより専門性の高い業務に専念でき、結果としてチームの労働環境も改善されました」
あるいは
「NPの介入は、診療体制の効率化に貢献し、医療アクセスを改善した可能性があります」
など。
主語を「患者さん」や「国民」に置き、タスクシフトを「結果」として語る。 この小さな工夫が、NPの価値を正しく伝えます。
結論
「NPの仕事はタスクシフトだ」という言葉は、NPの価値を矮小化し、未来を限定してしまう危険な罠です。
NPの仕事は、誰かの業務を代替することではありません。看護の心と医学の知識を携え、患者さんのすぐそばで、その人にとっての最善を追求することです。
その結果として、医師の負担が軽くなり、病院経営にも貢献する。
この順番を決して見失ってはいけないと思います。
私たちNPが自らをどう語るか。その言葉が、NPの未来を作ります。
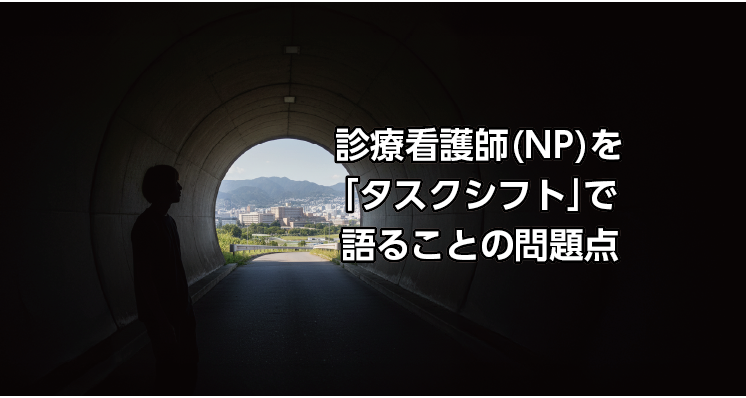
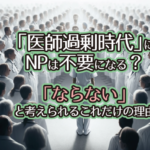

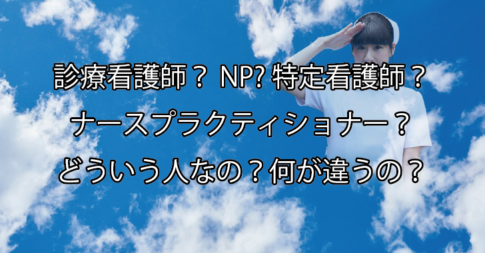

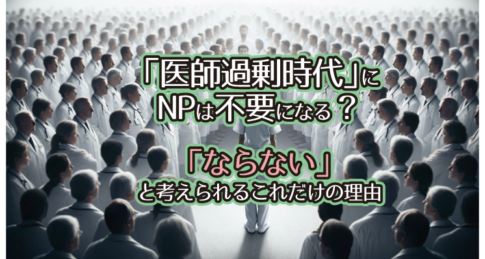
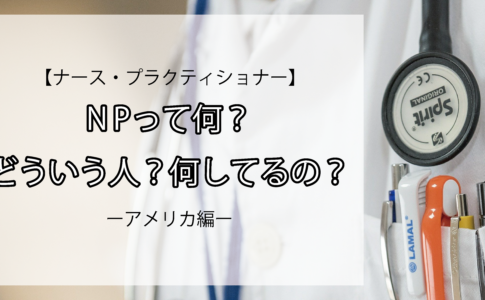
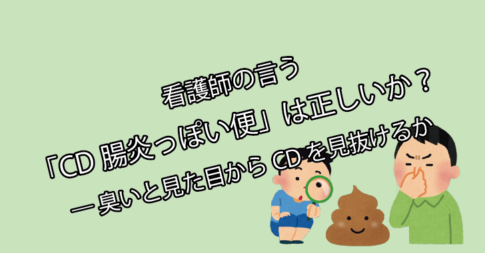





初めてコメントさせていただきます。
最近MRの方からも診療看護師(NP)に興味を持っていただき、講演等のお声かけをいただく機会が増えました。認知度アップにつながれば良いなと思い、お引き受けしてきましたが、最近は主旨に違和感を感じることも多くなりました。依頼内容を聞きながら、「医師のタスクシフトを意義としている診療看護師(NP)は少ないと思います」と思わず言ってしまったことがありました。後になり、結果的に反論してしまったことにモヤモヤしてしまいました。ですが、今日この記事を拝見できてよかったです。ありがとうございました。
コメントありがとうございます。
「思わず言ってしまった」というエピソード、とてもよくわかります。
私も同じような違和感を抱えていて、この記事を書きました。
「反論してしまった」とにモヤモヤされたとのことですが、私個人としては日本の片隅の診療看護師(NP)さんの発言は全く正当だと思います。
認知度は上がるが誤った形で認知されるのも困りますし…認知度を上げつつ正しい理解も促すというのは、実際難しいバランスだと思います。
私も、これらをどうバランスさせるか悩んでいます。
簡単な答えはありませんが、こうして同じ問題意識を持つ人がいることがわかるだけでも心強いです。ありがとうございました。
専門性、専門性と言っていますが、NPの専門性ってなんでしょうか?
専門性の発揮とありますが、NPの専門性ってなんでしょうか。この言葉を使っているということは、NPの猫さんはNPの専門性について確立した考えがあると思うので是非教えてください。
上と同じIPアドレスから2件のコメントをいただきましたので、こちらだけお答えします。
お急ぎだったようですね。
実に鋭いご意見ですが、お気付きの通り「NPの専門性とは何か」というのは、本稿では意図的に定義していません。むしろ明確に排除して書いています。
本稿のテーマは「NPをどう語るべきか」という言説論であり、専門性についての本質論ではありません。
NPの専門性は、Nurse Practitionerが活用されている海外においても多様で複雑に定義されています。
専門性が未確立な日本だからこそ、誤った枠組みを避けることが重要だと考えています。
ここで「私の考えるNPの専門性」を述べることは、本稿のテーマと外れますし、お互いに意味のあることとは考えづらいですがいかがでしょう。
記事の論旨をご理解いただければ幸いです。